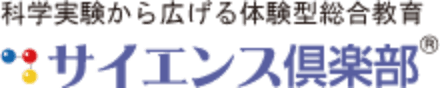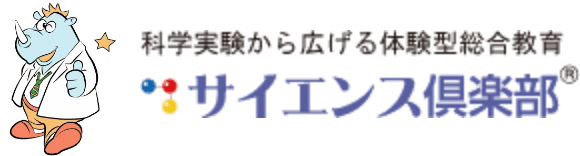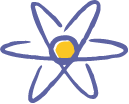
サイエンスキャンプ
EVENT

大自然には科学があふれています。
山や川や海などの大自然に飛び出して、化石や生物、植物などに触れたり、
学年の垣根を越えた仲間と一緒に協力しながら何かを成し遂げたりと、学校や普段の生活では経験できない “ワクワクドキドキの大冒険” 。
会員だけでなく、会員以外の方もご参加いただけます。自由研究のテーマ探しに最適です。
-

講師をはじめ複数名のスタッフが同行し、万全の体制で実習や身の回りのサポートをいたします。初めてのお泊りでも安心です!
-

現地の専門家や団体などの協力のもと、普段は絶対聞けない話しを聞いたり、サイエンスキャンプでしかできない体験にもチャレンジします。
-
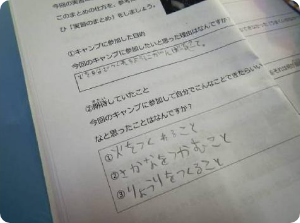
サイエンス倶楽部オリジナルワークブックもご用意。学習内容をまとめるだけでなく、自由研究にも活用できます。
はじめて参加される方・
参加を迷われてる方
7、8月のサイエンスキャンプ
ムシムシだいすき!
~朝から晩まで昆虫採集三昧。知恵と技で昆虫をゲットしよう!~
対 象:小学1年生~中学3年生
実習地:埼玉県秩父市
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/52,800円 会員/50,600円
世界で一番種類の多い動物は昆虫です。雑木林や野原など昆虫の生態を考えながらいろいろな場所を探って、様々な採集方法試してみよう。ライトトラップ採集にもチャレンジ、夜の雑木林のでの昆虫採集はドキドキの探険気分です。
奄美大島アドベンチャーキャンプ
~ここにはいつも新たな発見がある夏の奄美大島を満喫しよう!~
対 象:小学3年生~高校3年生
実習地:鹿児島県奄美市
集合解散:羽田空港
参加費(税込): 一般/216,700円 会員/214,500円
およそ200万年前、ユーラシア大陸とつながっていた奄美大島には、動物・植物の固有種が多数生息しています。 この島には常に何かしらの新しい発見があり、学びがあります。美しい自然の発見をはじめ、普段はあまり見せないような動物たちとの出会いまで。 まさに、「冒険島」といえます。
古代キャンプ!
~竪穴式や横穴式住居で寝泊まりしながら大昔を体験しよう!~
対 象:小学2年生~小学6年生
実習地:山梨県北都留郡小菅村
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/62,700円 会員/60,500円
原始古代の住居を舞台に「火」と「食」をテーマにした自然体験です。特に火を手に入れ、道具を考え、食料を確保して調理、保存するなど自然の中で遊びながらみんなで協力しながら学びます。川遊びや夜の他のいい体験も。
地底大冒険
~地底に眠る天然鉱物を掘り出し、さらに地底に潜って地球を感じよう!~
対象:小学3年生~高校3年生
実習地:福島県石川郡石川町
集合解散:東京駅
参加費(税込): 一般/小学生 90,200円 中高生 99,000円
会員/小学生 88,000円 中高生 96,800円
日本三大鉱物産地であり「鉱物の聖地」として知られる福島県石川町を訪れ、貴重な鉱物採集を行います。さらに近隣の洞窟では懐中電灯やろうそくの明かりを頼りに、冷たい水に浸かりながら鍾乳石の隙間をくぐったり、四つん這いになったりとまさに大自然をまじかに実感できるアドベンチャーキャンプです。
リバーキャンプ
~天然ウオータースライダーや魚釣りなど自然を思いっきり体感しよう!~
対 象:小学1年生~小学6年生
実習地:埼玉県秩父市
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/63,800円 会員/61,600円
自然の地形を生かしたフィールドで心も体も鍛えよう!遊びながら学ぶをモットーに自然体験を通じて仲間と一緒にリフレッシュ!
化石探検隊
~1500万年前の生き物たちが姿を現す。君はどんな化石と出会えるかな?~
対 象:小学1年生~小学6年生
実習地:埼玉県秩父市
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/51,370円 会員/49,170円
巨大ザメ(カルカロドン・メガロドン)や海獣(パレオパラドキシア)が見つかった地層を背景に、化石採集にチャレンジします。採集できた化石からわかることは何かを学びます。
ガーネットゲット
~魅惑的な光を放つ宝石、天然ガーネットとクリスタルを探し出そう~
対 象:小学1年生~中学3年生
実習地:長野県南佐久郡川上村
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/51,810円 会員/49,610円
鉱物好きには大好物の体験!ターゲットはガーネット(ザクロ石)とクリスタル(水晶)。八ヶ岳山麓の涼しい沢沿いで天然の鉱物採集に没頭してみよう!
【親子】ガーネットゲット
~親子で魅惑的な光を放つ宝石、天然ガーネットとクリスタルを探し出そう~
対 象:年長~中学3年生とその保護者・ご家族
実習地:長野県南佐久郡川上村
集合解散:現地
参加費(税込): 一般/93,500円 会員/91,300円(2名1組)
鉱物好きには大好物の体験!ターゲットはガーネット(ザクロ石)とクリスタル(水晶)。八ヶ岳山麓の涼しい沢沿いで天然の鉱物採集に没頭してみよう!
探険!恐竜と秘宝ヒスイの旅
~恐竜のボーンベットとフォッサマグナが伝えてくれる日本列島のナゾにせまる!~
対 象:小学3年生~高校3年生
実習地:福井県勝山市、新潟県糸魚川市
集合解散:東京駅
参加費(税込): 一般/小学生 134,200円 中高生 149,600円
会員/小学生 132,000円 中高生 147,400円
日本列島誕生のカギを握るフォッサマグナを間近に、大陸であった4億5千万年前の地球からの宝物を集めて貴重な岩石標本を完成しよう!また世界三大恐竜博物館の1つでもある福井恐竜博物館を訪れ地球や生命の科学についても学びます 。
いかだでGO!
~チーム自作のいかだで出航!みんなの英知を集結してのいかだレースは最高!~
対 象:小学1年生~中学3年生
実習地:群馬県藤岡市
集合解散:バスターミナル東京八重洲
参加費(税込): 一般/68,200円 会員/66,000円
浮かぶいかだを作るのが最低限のミッション!浮力を計算して素材を選んで、設計書作りや船の名前を決めて、旗を掲げて、さあ出発!
2024年度サイエンスキャンプ実績
| 時季 | 実習名 | 対象 | 実習地 | 泊数 |
|---|---|---|---|---|
| 春季 | さぐろう!海の生き物たち | 小学2年生~中学1年生 | 千葉県館山市 | 1泊2日 |
| サイエンス倶楽部オリジナル花火大会 | 年中~中学3年生 & 保護者 | 埼玉県秩父市 | 日帰り | |
| 化石発掘探検隊 | 小学2年生~中学3年生 | 埼玉県秩父市 | 1泊2日 | |
| 夏季 | 古代キャンプ! | 小学2年生~中学3年生 | 山梨県北都留郡小菅村 | 2泊3日 |
| ムシムシだいすき! | 小学1年生~中学3年生 | 埼玉県秩父郡長瀞町 | 1泊2日 | |
| リバーキャンプ | 小学1年生~中学3年生 | 埼玉県秩父市 | 2泊3日 | |
| いかだでGO! | 小学1年生~中学3年生 | 群馬県藤岡市 | 2泊3日 | |
| 化石探検隊 | 小学1年生~中学3年生 | 埼玉県秩父市 | 1泊2日 | |
| ガーネットゲット | 小学1年生~中学3年生 | 長野県南佐久郡川上村 | 1泊2日 | |
| 親子でガーネットゲット! | 年長~中学3年生とその保護者・ご家族 | 長野県南佐久郡川上村 | 1泊2日 | |
| ロハスキャンプ in アルソア | 年長~高校3年生とその保護者・ご家族 | 山梨県北杜市 | 2泊3日 | |
| 流星群と夏の星空キャンプ | 小学2年生~中学3年生 | 長野県南佐久郡川上村 | 2泊3日 | |
| へび研究の最前線を体験 | 中学2年生~高校3年生 | 群馬県太田市 | 日帰り | |
| 秋季 | 地底大冒険 | 小学3年生~高校3年生 | 福島県石川郡石川町 | 2泊3日 |
| 親子で木登り!ツリーイング | 小学1年生~中学3年生とその保護者・ご家族 | 群馬県藤岡市 | 日帰り | |
| 親子でゲット!化石採集にチャレンジ | 小学1年生~中学3年生とその保護者・ご家族 | 埼玉県秩父市 | 日帰り | |
| 親子で飛ばそう熱気球&ペットボトルロケット | 年中~小学6年生とその保護者・ご家族 | 東京都江東区 | 日帰り | |
| 冬季 | 雪と野生動物に出会う大冒険 | 小学3年生~高校生 | 北海道旭川市・美瑛町 | 2泊3日 |
| チャレンジ!解剖 | 小学4年生~高校生 | 長野県佐久市 | 2泊3日 | |
| 冬の星と星座キャンプ | 小学1年生~中学3年生 | 長野県南佐久郡 | 2泊3日 | |
| 春季 | サイエンス倶楽部オリジナル花火大会 | 年中~中学3年生 & 保護者 | 埼玉県秩父市 | 日帰り |